最近、ChatGPTをはじめとする生成AIが急速に普及し、私たちの生活や仕事に大きな変化をもたらしています。しかし、生成AIの便利な機能の裏側で、その電気代や消費エネルギーの大きさが電力問題として注目されていることをご存知でしょうか。
そもそも、なぜ消費電力が大きいのか、そして社会全体の電力需要が増えることで電力不足につながるのではないかという懸念も広がっています。また、個人が支払う利用料金やそれに伴う消費税とは別に、どのAIを選ぶかによって環境負荷が異なるという事実もあります。このような状況は、一部の電力銘柄にも影響を与え始めています。
この記事では、生成AIと電気代に関する様々な疑問に答え、その仕組みから社会的な影響、そして私たちが知っておくべき未来の展望まで、幅広く解説していきます。
- 生成AIが大量の電力を消費する根本的な理由
- AIの普及が電力需給や社会に与える具体的な影響
- 省エネ性能に優れたAIモデルや企業の取り組み
- 個人の利用と社会全体の電力問題の今後の展望
生成AIの電気代はなぜ高い?消費電力の課題
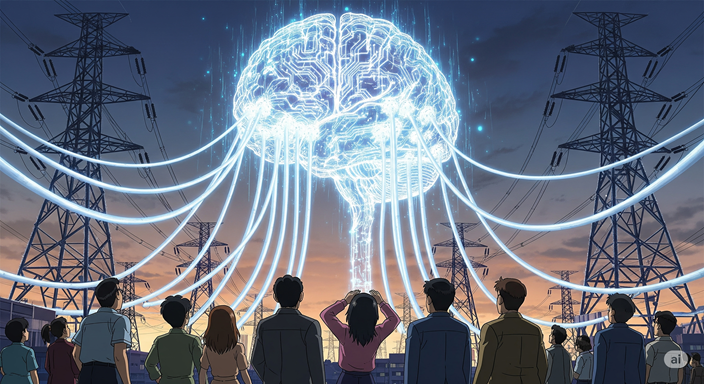
- なぜ消費電力が大きいのか?AIの仕組み
- ChatGPTなどAIモデル別の電力消費量
- AIの学習と推論で消費エネルギーは違う
- 生成AIの利用料金と電気代の関係性
- AIサービスの利用料金と消費税の扱い
なぜ消費電力が大きいのか?AIの仕組み
生成AIが多くの電力を消費する理由は、その根幹にある「大規模な計算処理」にあります。文章や画像を生成するために、AIは人間が到底及ばないほどの膨大な計算を瞬時に行っているのです。
この計算は、主に「学習(トレーニング)」と「推論(インファレンス)」という2つの段階で行われます。どちらの段階でも、高性能な半導体である「GPU(Graphics Processing Unit)」が何千、何万個も同時に稼働します。GPUはもともとコンピューターゲームの画像処理などに使われていましたが、並列計算能力が非常に高いため、AIの計算にも最適なのです。
具体的には、これらのGPUを大量に搭載したサーバーが、巨大な「データセンター」という施設に集められています。データセンターは、AIを動かすための頭脳が集まった場所と言えます。サーバー自体が大量の電力を消費するだけでなく、稼働時に発生する膨大な熱を冷やすための冷却システムにも多大な電力が必要となります。したがって、サーバーの稼働と冷却という2つの要因が、生成AIの大きな電力消費につながっているのです。
ChatGPTなどAIモデル別の電力消費量
生成AIと一口に言っても、その種類やモデルによって消費する電力の量には大きな差があります。より複雑で高性能なモデルほど、多くの計算を必要とするため、消費電力も増大する傾向にあります。
アメリカのスタンフォード大学が発表した研究によると、AIモデルが学習する際の消費電力とCO2排出量には、モデル間で桁違いの差が見られます。
| AIモデル名 | 学習時の消費電力量(MWh) | 学習時のCO2排出量(トン) | 備考 |
| BLOOM | 433 MWh | 25 トン | 米国人家庭の約41年分の電力に相当 |
| GPT-3 (ChatGPTの旧基盤) | 1,287 MWh | 502 トン | 原子力発電所1基の1時間分の電力を上回る |
※スタンフォード大学のレポート等に基づき作成
この表から分かるように、ChatGPTの基盤となったGPT-3モデルの学習には、BLOOMモデルの約3倍の電力が使われています。この1,287MWhという電力は、一般的な原子力発電所1基が1時間で生み出す電力量(約1,000MWh)を上回るほどの規模です。
さらに、文章生成だけでなく、画像や動画を生成するAIは、より多くの電力を消費する傾向があります。マサチューセッツ工科大学(MIT)の調査報告によれば、画像生成AIで画像を1枚作るエネルギーはテキスト生成より少なく済みますが、5秒間の動画を生成するためには、電子レンジを約1時間作動させるのに匹敵するエネルギーが必要になる場合もあるとされています。どのAIを選ぶかによって、環境への負荷が大きく異なることが分かります。
AIの学習と推論で消費エネルギーは違う
生成AIが電力を消費するプロセスは、大きく「学習」と「推論」の2つに分けられ、それぞれエネルギーの使われ方が異なります。
AIの性能を決める「学習」プロセス
「学習(トレーニング)」は、AIモデルに大量のデータを読み込ませ、賢くさせるための準備段階です。例えば、言語モデルであれば、インターネット上の膨大なテキストデータを学習し、言語のパターンや文法、知識を習得します。このプロセスは、モデル開発の初期段階で一度だけ行われますが、非常に高い計算能力を長時間にわたって必要とするため、エネルギー消費が極めて大きくなります。前述のGPT-3が学習に原発1基の1時間分以上の電力を要したというのは、この学習プロセスの話です。
私たちが利用する際の「推論」プロセス
一方、「推論(インファレンス)」は、学習済みのAIモデルがユーザーからの指示(プロンプト)に基づいて、実際に文章や画像を生成する処理のことです。私たちがChatGPTに質問を投げかけるたびに行われているのが、この推論プロセスです。一回あたりの推論で消費するエネルギーは学習に比べれば僅かですが、世界中で何億人ものユーザーが毎日利用するため、その合計量は膨大になります。従来のGoogle検索と比較して、生成AIによる1回の応答処理(推論)は10倍以上の電力を消費するケースもあると言われており、利用者の増加が全体の電力需要を押し上げる大きな要因となっています。
要するに、AIの電力問題は、開発時の大規模な「学習」と、日常利用で積み重なる「推論」の両面から考える必要があるのです。
生成AIの利用料金と電気代の関係性
多くのユーザーが気になるのは、「生成AIを使うと、自宅の電気代が上がるのか?」という点かもしれません。しかし、私たちが支払うサービスの「利用料金」と、AIがデータセンターで消費する「電気代」は直接結びついているわけではありません。
ChatGPTのようなクラウドベースの生成AIサービスを利用する場合、計算処理は開発元の企業が管理するデータセンターで行われます。そのため、AIを動かすための莫大な電気代は、サービス提供者であるOpenAI社などが負担しています。私たちがスマートフォンやパソコンでAIを利用する際に消費するのは、あくまで端末の動作や通信にかかる電力のみであり、AIの計算処理そのものによる電気代が個人の電気料金請求に上乗せされることはないのです。
では、月額制などで支払う「利用料金」は何に使われているのでしょうか。この利用料金は、データセンターの電気代や維持費だけでなく、高性能なGPUサーバーへの投資、AIを開発するための研究開発費、技術者の人件費など、サービスを提供するためのあらゆるコストを賄うために設定されています。したがって、利用料金と電気代は無関係ではありませんが、利用料金の一部が間接的に電気代の支払いに充てられている、と考えるのが正確です。
AIサービスの利用料金と消費税の扱い
日本国内で生成AIサービスを利用する際、その利用料金には消費税がどのように関わってくるのでしょうか。この点は、サービスを提供する事業者が日本国内か国外かによって扱いが異なります。
一般的に、日本の事業者が提供する有料サービスであれば、その利用料金には日本の消費税が含まれています。
一方で、OpenAI社(米国)やGoogle社(米国)など、国外の事業者が提供するサービスの場合は少し複雑です。事業者を対象とした取引(B2B)では「リバースチャージ方式」という仕組みが適用される場合がありますが、私たちのような個人消費者向けの取引(B2C)では、国外の事業者が日本の国税庁に登録し、日本の消費税を徴収して納税する「国外事業者による申告納税」が基本となります。
そのため、海外のAIサービスであっても、有料プランの支払い画面などで日本の消費税(Japanese Consumption Tax)が加算されているケースが多く見られます。利用料金の内訳を確認すると、本体価格とは別に消費税額が記載されていることが一般的です。このように、私たちが支払う利用料金には、サービスの対価だけでなく、国に納めるべき税金も含まれていることを理解しておくとよいでしょう。
生成AIの電気代が招く未来と企業の対策
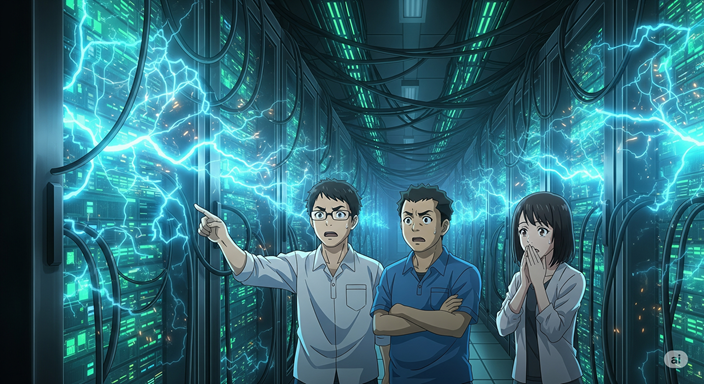
- データセンターの電力需要は今後どうなる
- 世界で深刻化するAIの電力問題とは
- AIの普及が招く電力不足への懸念
- 省エネはどのAI?軽量化モデルの登場
- 注目される電力銘柄とAIブームの影響
- 生成AIの電気代と持続可能な未来とは
データセンターの電力需要は今後どうなる
生成AIの普及に伴い、それを支えるデータセンターの電力需要は、今後爆発的に増加すると予測されています。
国際エネルギー機関(IEA)が2024年1月に発表したレポートは、この問題に警鐘を鳴らしています。レポートによると、世界のデータセンターやAIなどが消費した電力量は、2022年時点で約460TWh(テラワット時)でした。しかし、この需要は急カーブを描いており、2026年にはその倍以上である約1,000TWhに達する可能性があると指摘されています。この1,000TWhという数値は、日本全体の年間総消費電力量にほぼ匹敵する、驚異的な規模です。
また、金融大手のゴールドマン・サックスも、生成AIの進化がデータセンターの電力消費を2030年までに160%増加させると予測しています。この予測では、世界の総電力消費に占めるICT(情報通信技術)分野の割合が、現在の数パーセントから10%前後にまで拡大する可能性が示唆されました。
このように、多くの専門機関が、AIの進化が世界のエネルギー事情を大きく変える転換点になると見ています。この膨大な電力需要をどのように賄っていくのかが、今後の大きな課題となります。
世界で深刻化するAIの電力問題とは
前述の通り、データセンターの電力需要が急増することで、世界各地で「電力問題」が深刻化し始めています。この問題は単に電気が足りなくなるというだけでなく、環境や社会に多面的な影響を及ぼすものです。
第一に、環境への影響が挙げられます。急増する電力需要を賄うために、多くの地域では、石炭や天然ガスといった化石燃料による火力発電に頼らざるを得ない状況です。これにより、発電に伴うCO2排出量が増加し、地球温暖化を加速させるリスクがあります。データセンターが24時間365日稼働する必要があるため、天候に左右される太陽光や風力といった再生可能エネルギーだけで安定的に電力を供給するのは難しく、結果として化石燃料への依存度が高まりがちです。
第二に、電力網への負荷の問題があります。AI向けの巨大なデータセンターは、土地や冷却水の確保がしやすい特定の地域に集中する傾向があります。例えば、アメリカのバージニア州などはデータセンターの集積地として知られていますが、こうした地域では電力網が需要の急増に追いつかず、インフラの増強が急務となっています。
これらの理由から、生成AIの発展は、エネルギーの安定供給と環境保全という2つの側面から、世界共通の大きな課題を突きつけているのです。
AIの普及が招く電力不足への懸念
AIの電力問題がさらに進行すると、私たちの生活や企業活動に直接的な影響を及ぼす「電力不足」への懸念が高まります。
データセンターが「電力のブラックホール」と化し、地域の電力をごっそりと消費するようになると、他の産業や一般家庭に供給される電力が不足する事態も考えられます。実際に、一部の国や地域では、新たなデータセンターの建設計画に対して、電力会社が供給能力の限界を理由に難色を示すケースも出始めています。
もし電力不足が現実のものとなれば、企業にとっては事業の継続が困難になるリスクが生じます。特に、大量の電力を必要とする製造業などは大きな打撃を受ける可能性があります。また、私たち一般家庭にとっても、計画停電の増加や、電力需給の逼迫による電気料金の大幅な高騰といった形で影響が及ぶかもしれません。アメリカの一部の州では、データセンターのコストを賄うために一般家庭の電気料金が上乗せされる可能性も指摘されています。
このように、生成AIの恩恵を享受する一方で、その裏側ではエネルギーインフラの限界が近づいているという現実があります。技術の発展とエネルギーの安定供給のバランスをどう取るかが、社会全体にとって重要なテーマとなっています。
省エネはどのAI?軽量化モデルの登場
深刻化する電力問題に対応するため、AI業界ではエネルギー効率を高める技術開発が活発に進められています。特に注目されているのが、消費電力を抑えた「軽量AIモデル」の開発です。
巨大なモデルが必ずしも最善ではないという考えのもと、特定の用途に特化させたり、モデルの構造を効率化したりすることで、性能を維持しつつ消費電力を大幅に削減する取り組みが行われています。
その代表例が、NTTグループが開発した大規模言語モデル「tsuzumi」です。tsuzumiは、世界トップレベルの日本語処理性能を持ちながら、モデルの軽量化を徹底しています。その結果、GPT-3と比較して、学習にかかるコストを最大で300分の1に、推論コストを最大で約70分の1に抑えることが可能だとされています。
また、AIモデルの挙動を真似させて小さなモデルを作る「蒸留」という技術や、得意分野の異なる多数の小型モデルを連携させて問題を解決する「AIコンステレーション」といった新しいアプローチも研究されています。
このように、どのAIを選ぶかによって環境負荷は大きく変わります。今後は、AIの精度や機能だけでなく、「省エネ性能」もAIを選ぶ上で重要な指標の一つになっていくと考えられます。
注目される電力銘柄とAIブームの影響
生成AIの爆発的な普及は、株式市場、特に電力関連企業の株価、すなわち「電力銘柄」にも大きな影響を与え始めています。投資家たちは、AIがもたらす電力需要の急増を、電力会社にとっての新たなビジネスチャンスと捉えているのです。
AIを動かすデータセンターは、まさに電力を大量に消費する「優良顧客」です。今後、国内外でデータセンターの新設が相次ぐと見られており、それに伴って電力販売量が増加すれば、電力会社の収益は大きく向上する可能性があります。この期待から、安定供給能力を持つ大手電力会社や、データセンター向けのインフラ技術を持つ企業の株価が注目を集める場面が見られます。
一方で、これは電力会社にとって諸刃の剣でもあります。急増する需要に応えるためには、発電所の新設や送電網の増強といった莫大な設備投資が必要となります。また、社会からはCO2排出削減も強く求められており、再生可能エネルギーへの投資も欠かせません。これらのコスト負担が経営を圧迫するリスクも存在します。
このように、AIブームは電力業界に大きな成長機会をもたらす一方で、インフラ投資や環境対応といった課題も突きつけています。投資家は、これらのプラス面とマイナス面を総合的に判断し、各社の動向を注視している状況です。
生成AIの電気代と持続可能な未来とは

- 生成AIは膨大な量の計算処理を行うため大量の電力を消費する
- AIの電力消費は「学習」と「推論」の両方のプロセスで発生する
- 高性能なGPUを多数搭載したデータセンターが電力消費の主な場所である
- AIモデルによって消費電力は大きく異なり、GPT-3のような巨大モデルは特に多い
- IEAは世界のデータセンターの電力需要が2026年に2022年の倍以上になると予測
- 電力消費の増大は化石燃料への依存を高めCO2排出量を増やす懸念がある
- 一部の地域ではデータセンターへの電力供給が電力網を圧迫する問題が発生
- AIの普及は将来的に電力不足や電気料金高騰につながるリスクをはらむ
- 個人のAI利用料金がデータセンターの電気代と直接連動するわけではない
- 海外事業者のAIサービス利用料金にも日本の消費税が含まれる場合がある
- 電力問題への対策として省エネ性能を高めた軽量AIモデルの開発が進む
- NTTの「tsuzumi」などは消費電力を大幅に削減できるAIとして注目される
- データセンター側でも液体冷却などを用いてサーバーの冷却効率を高めている
- AIの電力需要増は電力会社のビジネスチャンスとなり電力銘柄が注目されている
- 技術の進歩とエネルギーの安定供給を両立させることが社会全体の課題である

