「地球が自転する理由はいったい何だろう?」と感じたことはありませんか。私たちは日々、昼と夜を経験していますが、その根本にある地球の回転について、深く考える機会は少ないかもしれません。
この記事では、そもそも地球はなぜ回り始めたのか、そして、コマのようになぜ止まらないのかという根源的な問いに答えます。また、地球の公転との違いや、季節を生み出す地軸が傾いている理由にも触れていきます。
さらに、時速約1700kmという地球の自転の速度、近年観測されているわずかな速度が急上昇している現象、そしてこれほどの高速回転を私たちがなぜ感じないのか、その不思議を解き明かします。もし地球が自転してなかったら、あるいはある日突然、自転が止まったらどうなるのか、という思考実験にも迫ります。
記事の最後には、家庭でも試せるかもしれない、地球の自転を感じる方法についてもご紹介します。この壮大な宇宙の仕組みについて、一緒に学びを深めていきましょう。
この記事でわかること
- 地球が46億年前から自転を続ける根本的な仕組み
- 自転の速度や地軸の傾きがもたらす私たちの生活への影響
- 高速で自転しているにもかかわらず私たちがそれを感じない理由
- 地球の自転に関する最新の動向や観測方法
そもそも地球が自転する理由は?起源と法則
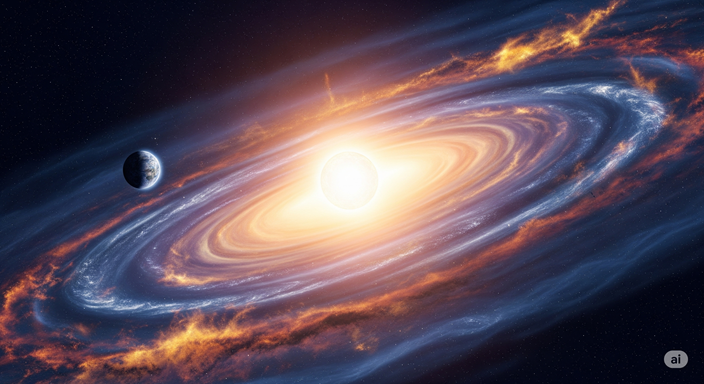
- 地球はなぜ自転を始めたのか
- コマと違う!自転がなぜ止まらないのか
- 地球の自転速度はどれくらい?
- 自転と公転はどう違うの?
- 地軸が傾いている理由と季節の関係
地球はなぜ自転を始めたのか
地球が自転している根本的な理由は、地球が誕生した約46億年前にさかのぼります。
もともと、太陽や地球を含む太陽系の星々は、宇宙空間に漂っていたガスや「ちり」が集まってできた巨大な雲(原始太陽系円盤)から生まれました。この雲は、誕生のきっかけとなった近くの超新星爆発の衝撃波などによって、全体がゆっくりと回転していたと考えられています。
その回転する雲の中で、ガスやちりが重力によって互いに引き寄せ合い、中心に集まって太陽が、そしてその周りで惑星の「卵」が形成されていきました。材料となった雲自体が回転していたため、その回転の勢い(角運動量)は、集まってできた惑星にも受け継がれます。バレリーナが腕を広げて回転している状態から腕を縮めると回転が速くなるように、広大な雲が小さな天体にまとまる過程で、回転はさらに強力になりました。
このように、地球は「回転する材料」から生まれたため、誕生した瞬間から自転をしていたのです。そして、太陽系の多くの惑星が同じ方向に自転しているのは、これらが同じ回転する雲から誕生した仲間であることの証拠とも言えます。
コマと違う!自転がなぜ止まらないのか
地球が誕生以来、46億年もの長きにわたって回り続けているのは、その回転を止めようとする力がほとんど働かないからです。
身近な例として、机の上で回したコマを考えてみましょう。勢いよく回したコマも、やがては回転が遅くなり、ついには倒れて止まってしまいます。これは、コマの軸と机、そして周りの空気との間に「摩擦力」が働くためです。摩擦力は、コマの回転を妨げるブレーキのような役割を果たし、回転のエネルギーを少しずつ奪っていきます。
一方、地球は広大な宇宙空間に浮かんでいます。コマにとっての机や空気のような、直接接触して摩擦を生じさせるものが周りにありません。そのため、回転を妨げる力が働かず、運動の状態を保ち続けようとする「慣性の法則」に従って、最初の回転の勢いをほぼ失うことなく回り続けているのです。
もちろん、地球には太陽や月の引力といった外からの力が全く働いていないわけではありません。しかし、これらの力は地球の自転を直接止めるような方向には作用しないため、自転の速さに大きな影響を与えることはありません。地球が回り続けているのは、何か特別な力が動かしているからではなく、「止めるものがないから」というのが答えになります。
地球の自転速度はどれくらい?
地球の自転速度は、赤道上において時速約1700kmにも達します。この驚異的な速さは、簡単な計算で求めることが可能です。
地球の赤道1周の距離は約40,000kmです。そして、地球が1回転するのにかかる時間は約24時間です。この距離を時間で割ると、「40,000km ÷ 24時間 ≒ 時速1667km」となり、一般的に時速約1700kmと言われています。
この速度がどれほど速いのか、身近な乗り物などと比較してみましょう。
| 対象 | 時速 | 地球の自転速度との比較 |
| 地球の自転(赤道上) | 約1700km | – |
| 音の速さ(マッハ1) | 約1225km | 地球の自転は音よりも速い |
| ジェット旅客機 | 約900km | 地球の自転は飛行機の約1.9倍 |
| 新幹線 | 約300km | 地球の自転は新幹線の約5.7倍 |
| 高速道路の自動車 | 約100km | 地球の自転は自動車の約17倍 |
このように、地球は私たちが想像する以上に、とてつもないスピードで自転していることがわかります。ちなみに、日本(東京)のような中緯度の場所では、赤道上よりも回転半径が小さくなるため、自転速度は時速約1300km程度となります。それでも、音速を超えるほどの速さであることに変わりはありません。
自転と公転はどう違うの?
地球の動きには「自転」の他に「公転」があり、この二つは明確に区別されます。
地球の自転とは
自転とは、地球そのものが、北極と南極を結ぶ軸(地軸)を中心に回転する運動のことです。この運動によって、地球上のあらゆる場所に昼と夜が交互に訪れます。地球が1回自転するのにかかる時間は約24時間(正確には23時間56分4秒)で、これを1日と定義しています。回転の向きは、北極側から見て反時計回りです。
地球の公転とは
一方、公転とは、地球が太陽の周りを軌道に沿って一周する運動のことです。この運動には約365日かかり、私たちが使う「1年」という単位の基準となっています。地球が太陽の周りを公転することで、後述する地軸の傾きと相まって、地上に季節の変化が生まれるのです。
要するに、自転は「地球自身の回転」であり、公転は「太陽の周りをまわる運動」です。コマに例えるなら、コマ自体がクルクル回っているのが自転で、そのコマが床の上を円を描きながら移動するのが公転に近いイメージとなります。この二つの運動が組み合わさることで、私たちの惑星の多様な環境が形作られています。
地軸が傾いている理由と季節の関係
地球の自転軸(地軸)は、地球が太陽の周りをまわる公転軌道面に対して、垂直ではなく約23.4°傾いています。このわずかな傾きが、私たちの暮らしに欠かせない「季節」を生み出す原因となっています。
もし地軸が傾いていなければ、太陽の光は常に赤道付近を真上から照らし、緯度によって受ける太陽エネルギーの量が一年中ほぼ同じになります。その結果、赤道付近は常に灼熱、極地は常に極寒となり、日本のような中緯度地域でも、はっきりとした季節の変化は起こらなかったと考えられます。
地軸が23.4°傾いていることで、地球が公転するにつれて、太陽光が強く当たる地域が変わっていきます。
- 北半球の夏: 北半球が太陽の方向へ傾いている時期です。太陽の光が真上近くから降り注ぎ、昼の時間が長くなるため、気温が上昇します。
- 北半球の冬: 北半球が太陽と反対の方向へ傾いている時期です。太陽の光は斜めから当たるようになり、昼の時間も短くなるため、気温が低下します。
このように、地球が公転軌道上のどの位置にあるかによって、地軸の傾きのおかげで各半球が受ける太陽エネルギーの量が増減し、春夏秋冬という季節の移り変わりが生まれるのです。なお、南半球の季節は北半球とは逆になります。
地軸が傾いた理由については、惑星が形成される最終段階で、火星ほどの大きさの別の原始惑星が地球に斜めから衝突したという「ジャイアント・インパクト説」が最も有力です。この巨大衝突が、地球に傾きを与えたと考えられています。
地球が自転する理由と私たちの暮らしの関係

- 高速回転をなぜ感じないのか
- 自転を感じる方法はフーコーの振り子
- もし地球が自転してなかったらどうなる?
- ある日突然、自転が止まったら?
- 近年、自転の速度が急上昇している?
- まとめ:慣性の法則こそ地球が自転する理由
高速回転をなぜ感じないのか
前述の通り、地球は赤道上で時速約1700kmという猛烈なスピードで自転していますが、私たちはその動きを全く感じることなく生活しています。これには明確な理由が二つあります。
第一に、私たち自身だけでなく、周りの大気や建物、海など、地表にあるもの全てが地球と一体となって、同じ速度で動いているからです。例えば、高速で走行中の新幹線に乗っていても、車内を歩いたり、物を置いたりすることに違和感はありません。これは、乗客も車内の空気も、全てが新幹線と同じ速度で移動しているためです。地球の自転もこれと同じ原理で、私たちと周囲の環境が一体となって動いているため、相対的な動きがなく、回転を体感できないのです。
第二に、地球の自転は非常に滑らかで、速度の変化がほとんどない「等速回転運動」だからです。私たちが乗り物で「動き」を感じるのは、主に加速・減速したり、カーブで揺れたりするときです。地球の自転にはそのような急な速度変化や振動がないため、動きとして認識することができません。
1秒あたりに回転する角度も0.0042°と極めて小さいため、視覚的に回転を捉えることも困難です。したがって、地球という巨大な乗り物に、私たちは生まれたときからずっと乗り続けているような状態であり、その動きを感じることはないのです。
自転を感じる方法はフーコーの振り子
私たちが自転を直接体感することはできませんが、地球が確かに回転していることを証明し、視覚的に「感じる」方法があります。その代表的なものが「フーコーの振り子」です。
これは、1851年にフランスの物理学者レオン・フーコーがパリのパンテオン寺院で公開実験を行い、地球の自転を証明した装置です。非常に長い糸の先におもりを吊るし、それを静かに振らせるという、構造はシンプルなものです。
もし地球が静止していれば、振り子は同じ平面上を往復し続けるはずです。しかし、実際には振り子の振動方向が、時間の経過とともにゆっくりと回転していきます。これは、振り子自身が慣性の法則によって同じ方向に揺れ続けようとするのに対し、その下の地球が自転して動いているために起こる現象です。見かけ上、振り子のほうが回っているように見えるのです。
回転する速さは緯度によって異なり、北極や南極では24時間で1周しますが、赤道上では回転しません。この回転の様子を観察することで、私たちは地球が自転しているという事実を間接的に、しかし明確に知ることができます。フーコーの振り子は、世界中の科学博物館などで見ることができ、地球の壮大な運動を実感させてくれる貴重な展示の一つです。
もし地球が自転してなかったらどうなる?
もし、地球が誕生時から自転をしていなかったとしたら、私たちの惑星は現在とは全く異なる姿になっていたでしょう。
まず、昼と夜のサイクルが劇的に変わります。地球の1日は、太陽の周りを1周する公転周期と同じ「1年」になります。つまり、地表のある場所では約半年間ずっと昼が続き、その後の半年間はずっと夜が続くという極端な環境になるのです。
昼が続く半球では、太陽に熱せられ続けて気温は摂氏100度を超える灼熱地獄となり、多くの水は蒸発してしまうと考えられます。一方で、夜が続く半球は、太陽光が全く当たらないため、宇宙空間に熱が奪われ続け、気温は氷点下数十度以下という極寒の世界になります。このような過酷な環境では、現在のような多様な生命が進化し、生存することは極めて困難だったはずです。
また、地球の自転によって生じる「コリオリの力」が存在しないため、大気の流れも大きく変わります。風は赤道から極へ、極から赤道へとまっすぐ吹くようになり、現在の台風や複雑な気象パターンは発生しません。海流も単純な流れとなり、地球全体の熱を循環させる役割が弱まってしまうでしょう。
自転は、惑星の形状にも影響を与えています。回転による遠心力で赤道付近がわずかに膨らんだ球体となっていますが、自転がなければより完全な球体に近くなります。このように、自転は昼夜のサイクルだけでなく、気候、環境、そして地球の形そのものを決定づける、非常に重要な要素なのです。
ある日突然、自転が止まったら?
もし、現在回転している地球がある日突然、ピタリと自転を止めてしまったら、それは想像を絶する大災害を引き起こします。これは「もし自転してなかったら」という仮定とは異なり、運動エネルギーが関わる、より破壊的なシナリオです。
慣性の法則により、地表にあるものすべて(人間、建物、大気、海水)は、自転が止まる直前の運動状態を維持しようとします。赤道付近では時速約1700kmという猛スピードで東に向かって動き続けようとするのです。
地球本体だけが停止し、その上のあらゆるものが超音速で東方向に投げ出される状態を想像してください。
- 地表: 建物は土台から吹き飛ばされ、山々も崩壊し、地表は完全に削り取られてしまいます。
- 大気と海洋: 大気は超音速の暴風となり、地表のすべてを破壊します。海水は巨大な津波となって大陸を洗い流し、地球全体を飲み込むでしょう。
- 生命: 地上のあらゆる生命は、衝撃と暴風、津波によって一瞬で絶滅すると考えられます。
自転が停止した後の地球は、片面が太陽に焼かれ、もう片面が凍りつく、静かで死の世界となります。前述の「自転してなかったら」の状況に近づきますが、そこに至る過程が壊滅的である点が異なります。
もちろん、これはあくまで思考実験であり、地球の自転を突然止めるような力は現実には存在しません。しかし、このシナリオを考えることで、私たちが当たり前だと思っている地球の自転が、いかに地上の平和と安定を保つ上で重要な役割を果たしているかが理解できます。
近年、自転の速度が急上昇している?

長期的には、月の引力による潮汐摩擦の影響で地球の自転は徐々に遅くなっています。しかし、ごく最近の観測では、逆に自転速度がわずかに速くなる(1日が短くなる)傾向が見られ、注目を集めています。
原子時計による精密な観測が始まって以来、地球の自転速度の変動はミリ秒単位で監視されています。2020年以降、1日が24時間より短くなる日が頻繁に観測されるようになりました。そして、国際地球回転・基準系事業(IERS)のデータによると、2022年6月29日には、原子時計の導入以来最も短い1日(24時間より1.59ミリ秒短い)が記録されています。2025年7月10日も、これに匹敵する短い日となりました。
この自転速度が速まる原因は完全には解明されていませんが、複数の要因が考えられています。
- 地球内部の動き: 地球の液体核(外核)と固体のマントルの相互作用の変化。
- 大気や海洋の動き: ジェット気流などの季節的な大気の変動。
- チャンドラー・ウォブル: 地球の自転軸そのものが起こす約433日周期の微小な揺れ。
この速度上昇が続くと、世界の基準時刻と地球の実際の回転とのズレを補正するために、「負のうるう秒」(1秒を引く調整)が必要になる可能性が史上初めて議論されています。しかし、一方で、地球温暖化による極地の氷の融解は、地球の質量バランスを変化させ、自転速度を遅くする効果があることも指摘されています。
このように、地球の自転速度は様々な要因が複雑に絡み合って変動しており、科学者たちはそのメカニズムの解明に取り組んでいます。ミリ秒単位の変化ですが、私たちの時間の基準に関わる重要な研究分野なのです。
まとめ:慣性の法則こそ地球が自転する理由
この記事では、地球がなぜ、そしてどのようにして自転しているのかについて、多角的に解説してきました。最後に、本記事の重要なポイントを箇条書きでまとめます。
- 地球の自転の起源は約46億年前の太陽系誕生時にさかのぼる
- 元となったガスやちりの雲が回転しておりその勢いが受け継がれた
- 宇宙空間には摩擦がほとんどなく慣性の法則で回り続けている
- 何か特別な力が地球を回しているわけではない
- 自転は地球自身の軸周りの回転で公転は太陽の周りの運動
- 地軸が公転軌道に対し約23.4°傾いているため季節が生まれる
- 地軸の傾きは巨大な天体の衝突が原因とする説が有力
- 赤道上の自転速度は時速約1700kmで音速を超える
- 私たちや大気が一緒に動いているため高速回転を感じることはない
- フーコーの振り子を使えば地球の自転を視覚的に確認できる
- もし自転がなければ昼と夜が半年ごとになり過酷な環境になる
- 自転が突然止まると地上の全てが超音速で吹き飛ぶ大災害となる
- 長期的には自転は遅くなっているが近年はわずかに速まる傾向にある
- 自転速度の変動は原子時計で精密に観測されている
- 地球が自転する理由は壮大な宇宙の法則と歴史の結果である


コメント