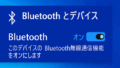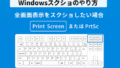こんにちは、「Windowsサポート」の管理人です。ついにWindows Server 2025が登場しましたね!
ITインフラの話題って、普段はあまり表に出てこないですけど、新しいOSが出るとなると話は別です。特に「windowsserver2025のリリース日は結局いつなの?」と気になっていた方は多いんじゃないでしょうか。私もその一人で、公式の発表をずっと待っていました。
リリース日が分かると、今度はサポート期限や、どんな新機能があるのか、エディションの違いはどうなるのか、といった点が気になってきますよね。さらに、導入するためのシステム要件や、既存のサーバーからのアップグレードは可能なのか、そして何より価格やライセンス体系がどう変わるのか…考えることがたくさんあります。
この記事では、私なりに調べたWindows Server 2025のGA(一般提供開始日)に関する情報や、注目の新機能について、分かりやすくまとめてみました。
- Windows Server 2025の正式なリリース日
- メインストリームと延長のサポート期限
- 注目の新機能(ホットパッチなど)
- 新しいライセンスモデルとエディションの違い
windowsserver2025 リリース日の公式発表

まずは、皆さんが一番気になっている「リリース日」に関する公式情報です。OSの導入計画を立てる上で、この日付がすべての基準になりますからね。
GA(一般提供開始日)はいつ?
Microsoftから公式に発表されたWindows Server 2025の一般提供(GA)開始日は、2024年11月1日です。
この日付をもって、企業は新しいサーバーOSの導入を正式に開始できるようになった、ということですね。
ちなみに、OSのコードが完成したことを意味する「製造リリース(RTM)」は、2024年5月27日に行われていたようです。GAまで約5ヶ月も期間が空いていますが、これはMicrosoftがまず自社のAzureで大規模に検証したり、DellやHPEといったハードウェアメーカーがドライバーを準備したりするための「熟成期間」だったみたいですね。
私たち一般企業が使う頃には、すでにある程度「実戦検証済み」になっている、と考えると安心感があるかも知れません。
サポート期限とライフサイクル
リリース日と同じくらい大事なのが、「いつまでサポートされるのか」という点ですね。Windows Server 2025は、従来のLTSC(長期サービスチャネル)リリースです。
これは、5年間のメインストリームサポートと、5年間の延長サポートが提供される、おなじみのモデルです。延長サポートが終了する日が、セキュリティ更新が止まる「崖」になるので、この日付は絶対に覚えておかないといけません。
| イベント | 日付 |
|---|---|
| 一般提供開始日 (GA) | 2024年11月1日 |
| メインストリームサポート終了日 | 2029年11月13日 |
| 延長サポート終了日 | 2034年11月14日 |
2034年11月14日。これが次の大きな目標日になりますね。まだまだ先のように感じますが、サーバーの移行計画は早めに立てておくのが吉かなと思います。
プレビュー版からの流れ
GAに至るまでには、いくつかのステップがありました。開発やテストのための最初の「Insider Previewビルド」がリリースされたのは、2024年1月26日だったようです。
そこから約10ヶ月かけて、RTM(5月27日)、そしてGA(11月1日)へと進んできたわけですね。バージョンとしては「24H2」という名前で識別されています。
導入のためのシステム要件
「よし、じゃあ早速インストールだ!」となる前に、ハードウェアの要件チェックが必要です。Microsoftが公表している「最小」要件は、CPUが1.4 GHz 64ビットプロセッサ、RAMが512MB(Server Core)など、かなり低く設定されています。
ですが、これはあくまで「起動するだけ」の数値かなと。
推奨される(というか現実的な)要件
実際にGUI(デスクトップエクスペリエンス)で運用するなら、RAMは最低でも4GB、できれば16GB以上、ブートドライブもSSD(32GB以上、推奨は160GB以上)は欲しいところですね。
それともう一つ、非常に重要な「隠れた」要件があります。
古いCPUではインストール不可!
Windows Server 2025は、CPUが「SSE4.2」および「POPCNT」という命令セットをサポートしている必要があります。
これが何を意味するかというと、だいたい2008年より前に製造された古い64bit CPU(例えばIntel Core 2 Duo世代など)では、たとえクロック周波数を満たしていてもインストールできない、ということです。これは実質的な足切りですね。
また、Credential Guardのような高度なセキュリティ機能を使うには、TPM 2.0やUEFI(セキュアブート対応)も必須となります。最近のサーバーならまず問題ないと思いますが、古いハードウェアを流用しようと考えている場合は注意が必要ですね。
2019からのアップグレードパス
新規インストール(クリーンインストール)が推奨されがちですが、「今動いているサーバーをそのままアップグレードしたい」というニーズも多いと思います。
今回、サポートされるアップグレードパスがかなり拡大されました。
- Windows Server 2019 → 2025 (OK)
- Windows Server 2022 → 2025 (OK)
もちろん、この2つからの直接インプレースアップグレードはサポートされています。
そして驚きなのが、Windows Server 2012 R2からも直接2025へアップグレード可能になった点です。2016、2019、2022を飛び越えて一気に最新化できるというのは、大きなニュースかなと思います。
とはいえ、個人的にはやはりサーバーOSのアップグレードはリスクが伴うと思うので、可能ならクリーンインストールしてデータを移行する方法を選びたいところです。
windowsserver2025 リリース日以降の機能

リリース日が確定したところで、次は「何が新しくなったのか?」という中身の話ですね。私が特に「おっ」と思った新機能や変更点をピックアップしてみました。
注目すべき新機能の概要
まず、見た目や使い勝手が結構変わっています。
デスクトップエクスペリエンス(GUI)が、Windows 11のスタイルに更新されました。スタートメニューの位置とか、アイコンのデザインとかですね。
さらに、サーバーOSとしては初めてBluetoothがネイティブサポートされました。データセンターで使うことはないかもですが、支店の隅に置かれたサーバーをメンテナンスする時なんかは、ワイヤレスキーボードが使えて便利かもしれません。
また、管理ツールにも変化があります。
- OpenSSH Server: デフォルトで含まれるようになり、Linux/Unix系との連携がスムーズに。
- Windows Terminal: 最新のコマンドプロンプトやPowerShellをタブで管理できるアレが、デフォルトになりました。
- DTrace: パフォーマンス分析ツール「dtrace」がネイティブ搭載され、トラブルシューティングが強化されたようです。
ホットパッチの仕組みと価格
今回のリリースで最大の目玉機能が、この「ホットパッチ」だと思います。
これは、OSを実行したまま(つまり再起動せずに)セキュリティパッチを適用できる技術です。サーバー管理者の長年の夢だった「ダウンタイム(停止時間)の削減」がついに実現するかも、と期待されています。
ただし、この機能、オンプレミス環境で使うにはいくつかの条件とコストがかかります。
ホットパッチの利用条件(オンプレミス)
- サーバーが Azure Arc(Azureの管理サービス)に接続されていること。
- OSライセンスとは別に、有料のサブスクリプションとして提供されること。
価格は、月額 $1.50 / 物理コア となっています(2025年7月1日から課金開始)。
毎月再起動が不要になるわけではなく、3ヶ月に1回は再起動が必要な「ベースラインアップデート」があり、間の2ヶ月が再起動不要のホットパッチになる、というサイクルのようです。それでも、計画停止が年12回から年4回に減るのは大きいですね。
Microsoftとしては、この「ホットパッチ」を人質に(笑)、オンプレミスのサーバーをAzure Arcに接続させたい、という戦略が透けて見えますね。
エディションごとの違い
エディションは主に「Standard」と「Datacenter」の2種類です。一番の違いは、やはり「仮想化権限」です。
- Standard Edition: 2つの仮想マシン(OSE)またはHyper-Vコンテナの実行権限が含まれます。
- Datacenter Edition: 仮想マシンの実行権限が無制限です。
物理サーバー上でたくさんのVMを動かすならDatacenter、VMが2台までか物理サーバーとして使うならStandard、というのが基本的な選び方ですね。
他にも、高度なストレージ機能(Storage Spaces Direct)やネットワーク機能(SDN)はDatacenter限定ですが、嬉しい変更点もあります。
ReFS(新しいファイルシステム)の重複排除と圧縮機能が、これまでDatacenter限定でしたが、Windows Server 2025ではStandard Editionでも利用可能になりました!これは中小規模のファイルサーバーなどで、ストレージ効率を上げるのに役立ちそうです。
新しいライセンスモデルとは
ライセンスの買い方も新しくなりました。従来の「永続ライセンス」に加えて、「従量課金(Pay-as-you-go, PAYG)」モデルがオンプレミス向けに導入されました。
1. 従来の永続ライセンス(コアベース)
これは今まで通り、サーバーに搭載されている物理CPUコア数に基づいてライセンスを購入するモデルです。最低16コア分のライセンスが必要です。そして、このサーバーにアクセスするユーザーやデバイスごとにCAL(クライアントアクセスライセンス)も別途購入する必要があります。
2. 新しい従量課金(PAYG)
これは、オンプレミスのサーバーをAzure Arcに接続し、OSのライセンス料金をAzureの利用料として月額で支払うモデルです。StandardとDatacenterの区別なく、同一料金($33.58 / コア / 月 または $0.046 / コア / 時)のようです。
一見、永続ライセンスより高く見えますが、このPAYGモデルにはCALが不要という最大のメリットがあります。
例えば、アクセスするユーザーが非常に多い(数百〜数千人)リモートデスクトップサーバー(RDS)のような環境では、永続ライセンス+大量のCALを買うよりも、PAYGモデルの方がトータルコストが安くなる可能性がある、ということですね。
ライセンスに関するご注意
ライセンスの計算は非常に複雑です。特にCALが不要になるケースや、仮想化環境でのライセンス(DatacenterとStandardの分岐点)など、実際の導入シナリオによって最適な選択は異なります。
ここで紹介したのはあくまで概要ですので、正確なライセンス費用や条件については、必ずMicrosoftのライセンスパートナーや専門家にご相談ください。
セキュリティとパフォーマンス強化
もちろん、中身も進化しています。特にActive Directory(AD)と仮想化(Hyper-V)の進化がすごいなと感じました。
Active Directory (AD) の進化:
ADのデータベースページサイズが、従来の8KBからオプションで32KBを選べるようになりました。これは、Entra ID(旧Azure AD)と同期する情報が増え続けている現代のハイブリッド環境に対応するためだそうです。まさに「ハイブリッドIDのハブ」としての進化ですね。
Hyper-Vの超スケールアップ:
Hyper-Vで作成できる仮想マシンの上限が、文字通り「桁違い」になりました。
- VMあたりのメモリ: 最大 240 TB (テラバイト)
- VMあたりの仮想プロセッサ: 最大 2,048 vCPU
「モンスターVM」と呼べるレベルで、巨大なデータベースなども仮想化で動かせる時代になったんだなと実感します。
セキュリティのデフォルト強化:
「Credential Guard」がデフォルトで有効になったり、LDAP通信がデフォルトで暗号化されたりと、初期状態からセキュリティが高められています(ゼロトラストの原則、というらしいです)。
windowsserver2025 リリース日まとめ
あらためて、windowsserver2025のリリース日は2024年11月1日です。そして、延長サポート終了日は2034年11月14日となります。
今回のリリースは、単なるOSのアップデートというよりは、MicrosoftがオンプレミスのサーバーをいかにAzureの管理下に統合していくか、という強い意志を感じるものでした。
「ホットパッチ」や「PAYGライセンス」といった魅力的な新機能は、すべて Azure Arcへの接続 が前提となっています。これからのサーバー管理は、クラウドとの連携を抜きには語れない、ということなんでしょうね。
まずはリリース日を把握しつつ、自社の環境にどの新機能やライセンスモデルが合うのか、じっくり検討していく必要がありそうです。