こんにちは!Windowsサポートの管理人です。
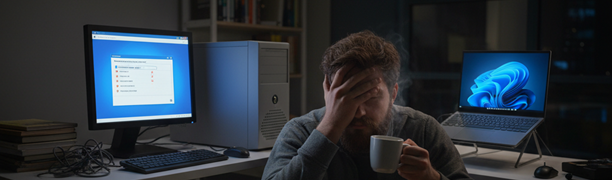
Windows 11が登場してからしばらく経ちますが、「自分のPCもそろそろアップグレードしようかな」と考えている方も多いんじゃないかなと思います。でも、いざ試してみたら「このPCは現在、Windows 11 のシステム要件を満たしていません」という無情なメッセージが…。
Microsoft公式の「PC正常性チェック」アプリを使ってみて、原因がTPM 2.0やセキュアブート、あるいはCPUが非対応となっていることを知り、どうすればいいか途方に暮れているかもしれませんね。特に、2025年10月にはWindows 10のサポート終了も控えているので、セキュリティ面での不安も大きいと思います。
この記事では、windows11 アップグレードできないpc をどうするべきか、その具体的な原因の特定方法から、BIOS設定による公式な対処法、さらには非公式な方法やWindows 10を使い続ける場合の選択肢まで、私が調べた情報を分かりやすく解説していきますね。
- アップグレードできない根本的な原因(TPM・CPUなど)
- BIOS設定を変更して公式要件を満たす方法
- 要件を回避する非公式なインストールの危険性
- Windows 10サポート終了後の現実的な選択肢
windows11 アップグレードできないpc どうする?原因と公式対処法
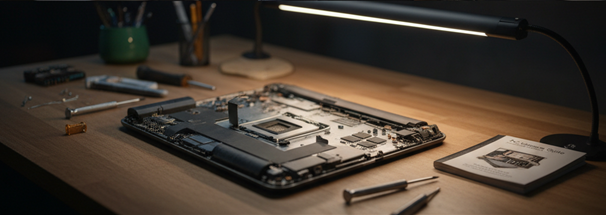
まず最初に、なぜアップグレードが拒否されてしまうのか、その原因をはっきりさせる必要がありますね。そして、もしそれが設定変更だけで解決できる「公式な」対処法があるなら、それを試すのが一番安全です。
Windows 10 サポート終了のリスク
本題に入る前に、この問題の「緊急性」について少しだけお話しさせてください。
ご存知の通り、Windows 10のサポートは2025年10月14日をもって終了します。これはもう決定事項なんですね。
サポートが終了すると、具体的に何が起こるかというと、
- セキュリティ更新プログラムが提供されなくなる
- 機能の追加や不具合の修正がなくなる
- Microsoftの公式サポートが受けられなくなる
という状態になります。PCがすぐに動かなくなるわけではないですが、セキュリティの「盾」がない無防備な状態でインターネットに接続し続けることになります。
これは、ウイルス感染や個人情報の流出、ランサムウェア(身代金要求型ウイルス)の被害に遭うリスクが劇的に高まることを意味します。だからこそ、「アップグレードできないPCをどうするか」は、「どうやってセキュリティを維持するか」という問題でもあるんですね。
アップグレードできない原因の特定方法
では、なぜあなたのPCはアップグレードできないのでしょうか?
「CPUが古いからダメだ」と最初から諦めるのは早いかもしれません。まずは、Microsoftが公式に提供している「PC正常性チェック」アプリを使って、正確な原因を突き止めるのが一番です。
このツールは、Windows Updateの画面などからダウンロードできます。インストールして「今すぐチェック」を押すだけで、何が要件を満たしていないのかを具体的に教えてくれます。
よくある不合格の理由は、以下の3つですね。
- 「TPM 2.0 がこの PC でサポートされ、有効になっている必要があります」
- 「PC はセキュア ブートに対応している必要があります」
- 「プロセッサは現在、Windows 11 でサポートされていません」
この結果によって、次に取るべき行動がまったく変わってきます。
基本的な空き容量もチェック!
意外な見落としがちな点として、ストレージ(SSD/HDD)の空き容量不足があります。Windows 11のアップグレードには十分な空き容量(最低でも64GB以上が推奨)が必要です。もし容量がカツカツなら、不要なファイルを削除したり、ディスククリーンアップを試したりしてみてくださいね。
TPM 2.0の確認と有効化
「TPM 2.0が見つかりません」と表示された場合、多くの人が「あ、自分のPCには載ってないんだ」と思ってしまうかもしれません。
でも、ちょっと待ってください!
TPM 2.0は、ここ数年のPCならCPUに内蔵されている(ファームウェアTPMと呼ばれます)ことがほとんどです。ただ、それがBIOS(バイオス)またはUEFI(ユーイーエフアイ)というPCの根本的な設定画面で「無効」になっているだけ、というケースが非常に多いんです。
Intel系CPUなら「Intel PTT (Platform Trust Technology)」、AMD系CPUなら「AMD fTPM」という名前の項目になっていることが多いですね。
もしPC正常性チェックでTPMが原因と出たら、まずはBIOS/UEFI設定を確認してみる価値は十分にあります。
セキュアブートのBIOS設定
「セキュアブートに対応していません」と表示された場合も、TPM 2.0と理屈は同じです。
セキュアブートは、PCの起動時に怪しいプログラムが割り込むのを防ぐための重要なセキュリティ機能です。これも、TPM 2.0と同様に、BIOS/UEFI設定で意図的に「無効」になっている可能性があります。
BIOS/UEFIメニューの「Boot」や「Security」といったタブの中に「Secure Boot」という項目があるはずなので、ここを「Enabled(有効)」に変更してみましょう。
セキュアブートを有効にするための前提条件
セキュアブートを有効にするには、いくつか前提条件があります。
- BIOSモードが「UEFI」であること: もし「Legacy」や「CSM」といった古いモードになっている場合は、「UEFI」に変更する必要があります。
- ディスク形式が「GPT」であること: OSが入っているドライブの形式が古い「MBR」だと、UEFIモードで起動できません。Windows 10の標準ツール(MBR2GPT)でデータを消さずに変換することも可能ですが、少し専門的な知識が必要になりますね。
まずは「システム情報」(msinfo32で起動できます)を開き、「BIOSモード」と「セキュア ブートの状態」を確認してみるのが早いです。
TPM 2.0とセキュアブート、この2つを有効化するだけで、今まで「非対応」と言われていたPCが、あっさりと「対応済み」に変わることが本当によくあります。これが一番安全で、Microsoftも推奨する「公式な」解決策ですね。
CPUが非対応と表示された場合
これが、一番厄介な「ハードブロック(物理的な壁)」です。
「プロセッサは現在、Windows 11 でサポートされていません」と表示された場合、これは「BIOS設定でどうにかなる問題ではない」ことを意味します。
Microsoftは、Windows 11でサポートするCPUの公式リストを公開していて、原則としてIntelなら第8世代Coreプロセッサ以降、AMDならRyzen 2000シリーズ以降としています。
「え、Intel第7世代でも十分高性能なのに!」と思う気持ちは、私もよく分かります。実際、性能差はそこまで大きくないモデルもありますからね。ただ、Microsoftが線を引いたのは性能そのものよりも、Windows 11の新しいセキュリティ機能(VBSなど)を、ハードウェアレベルで効率よくサポートしているかどうか、という点なんだそうです。
もしCPUが原因で非対応となった場合、公式なアップグレードパスは「存在しない」ということになります。その場合、次のセクションで解説する「非公式な手段」か「アップグレードを諦める」かのどちらかを選択することになります。
windows11 アップグレードできないpc どうする?非公式な手段と最終選択肢

さて、BIOS/UEFI設定を変更してもダメだった、あるいは原因が「CPU非対応」という物理的な壁だった場合。それでもWindows 11をインストールする「非公式な方法」と、アップグレード自体を諦めて「別の道」を探す選択肢が出てきます。
Rufusを使った非公式インストール
「どうしてもこのPCでWindows 11を使ってみたい!」という方向けに、システム要件チェックを回避してインストールを強制実行する方法があります。
いくつか方法はありますが、比較的安全で手順が確立されているのが、「Rufus(ルーファス)」というフリーソフトを使う方法です。
Rufusは、Windowsのインストール用USBメモリを作成するための定番ソフトですが、最新版にはWindows 11のインストールメディアを作る際に、「TPM 2.0やセキュアブート、CPUの要件チェックを無効化する」というパッチを自動で適用してくれる機能が搭載されています。
手順としては、
- Windows 11の公式ISOファイルをMicrosoftからダウンロードする。
- Rufusをダウンロードして起動する。
- USBメモリをPCに挿し、RufusでISOファイルを選択する。
- 「スタート」を押すと出てくるカスタマイズ画面で、「4GB以上のRAM、セキュア ブートおよび TPM 2.0 の要件を削除」にチェックを入れる。
- USBメモリを作成し、そのUSBメモリからPCを起動してWindows 11をインストールする。
という流れですね。これを使えば、公式には非対応のPC(例えばIntel第7世代CPUのPC)にも、Windows 11をインストールすること自体は可能です。
レジストリ編集による回避方法
もう一つの有名な方法が、Windows 10の「レジストリ」を直接編集して、アップグレード時のチェックを回避する方法です。
Windows 10のレジストリエディター(regedit)を起動し、特定の場所(HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup)にAllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPUという名前の値を作成し、そのデータを「1」にする、というものです。
この設定をしてから再起動し、再度アップグレードを試みると、TPMやCPUのチェックがスキップされる、と言われています。
他にも、インストールISOファイルの中にある「appraiserres.dll」というチェック用のファイルを削除(または置き換え)する方法などもありますが、どれもMicrosoftが想定していない「裏ワザ」であることには変わりありません。
非公式アップグレードの重大なリスク
Rufusやレジストリ編集で「インストールできた!やった!」と喜ぶのは、残念ながら早いかもしれません。これらの非公式な方法には、非常に重大なリスクが伴います。
これは本当に重要なことなので、Microsoftが公式に警告している内容を、私の言葉でまとめさせてもらいますね。
【警告】非公式アップグレードの代償
Microsoftは「要件を満たさないPCへのインストールは推奨しない」と明確に警告しています。その理由は以下の通りです。
- サポート対象外になる: 当たり前ですが、非公式な方法でインストールしたPCは、MicrosoftとPCメーカー両方のサポート対象外となります。何かあっても「自己責任」です。
- システムの不安定化: Windows 11は、TPM 2.0やセキュアブートが「ある」前提で設計されています。その基盤なしに動かすと、システムが頻繁にクラッシュしたり、特定の機能(Windows Helloの顔認証など)が動かなくなったりする可能性が非常に高いです。
- 最大のリスク:更新プログラムが停止する可能性: これが最も致命的です。Microsoftは、非対応PCには将来のセキュリティ更新プログラムや機能アップデートを提供しない可能性があると明言しています。
考えてみてください。私たちがWindows 11にしたい理由の一つは、「Windows 10のサポートが切れて、セキュリティ更新が止まるのが怖いから」でしたよね?
それなのに、わざわざ危険を冒して非公式にWindows 11にアップグレードした結果、「Windows 11環境でセキュリティ更新が止まる」という、本末転倒な状況に陥る可能性があるんです。
セキュリティリスクを回避するための行動が、別のセキュリティリスクを生む…これは、メインで使うPCや大切なデータが入っているPCでは、絶対に取るべき選択肢ではない、と私は思います。
Windows 10 ESUで延命する
「非公式な方法はリスクが高すぎる。でも、すぐに買い替える予算もない…」
そういった状況のユーザーが非常に多いことを見越して、MicrosoftはWindows 10に対して「延命措置」を用意してくれました。それが「ESU (Extended Security Updates)=拡張セキュリティ更新プログラム」です。
これは、2025年10月のサポート終了後も、有償でセキュリティ更新プログラムだけを受け取り続けられる公式なプログラムです。
従来は法人向けがメインでしたが、Windows 10(22H2)では初めて、私たち個人ユーザーも対象になりました。
個人向けESUの概要
- 期間: 最大1年間(2026年10月まで)セキュリティ更新が延長されます。
- 内容: あくまで「緊急」「重要」なセキュリティパッチのみ。新機能の追加やテクニカルサポートはありません。
- 価格 (日本国内):
- 実質無料オプション: Microsoftアカウントでサインインし、PC設定をクラウドに同期しているユーザーは、追加費用なし(無料)で登録される見込みです。
- Microsoft Rewards: 1,000ポイントと交換。
- 購入: 1回限りの支払いで $30 USD (または相当額)。
※料金や条件の詳細は、必ずMicrosoftの公式サイトで最新の情報をご確認ください。
このESUを利用すれば、セキュリティの心配をせずに、新しいPCへの買い替えを検討するための時間的な猶予を「1年間」確保できます。非対応PCをお持ちの方にとって、最も現実的で安全な「次の一手」かもしれませんね。
最新PCへの買い替え
これはもう、最も根本的で、最も安全な解決策ですね。MicrosoftもPCメーカーも、一番推奨している方法です。
古いPCから、最初からWindows 11が搭載されている新しいPCに買い替える、という選択肢です。
メリットは言うまでもありません。
- Windows 11のセキュリティ機能を100%享受できる。
- メーカーの正規保証が受けられる。
- 最新のCPUや高速なSSDで、PCの動作自体が劇的に快適になる。
もちろん、新しいPCを購入するための「コスト(費用)」が発生しますし、古いPCからデータや設定を引っ越しする「手間」もかかります。ですが、セキュリティや快適性、将来性を考えた場合、最も確実な投資かなと思います。
Linux OSへの移行
「PC本体はまだ動くのにもったいない!」「でもコストは1円もかけたくない!」
そんな技術的な探究心がある方には、OS自体をWindows 10から、無償で利用できる「Linux(リナックス)」に入れ替えるという選択肢もあります。
Ubuntu(ウブントゥ)やLinux Mint(リナックスミント)といったディストリビューションは、初心者にも使いやすく、Windowsに似た操作感のものも増えています。もちろん、現在も活発に開発が続けられているので、セキュリティアップデートもきちんと提供されます。
ただし、デメリットも明確です。
- Windowsとは操作感が根本的に異なる。
- Microsoft OfficeやAdobeソフトなど、Windows専用のソフトは原則動かない(代替ソフトへの移行が必要)。
- 新しいOSの操作を学ぶ学習コストがかかる。
サブPCとして余生を送らせる、といった用途には面白い選択肢かもしれませんね。
windows11 アップグレードできないpc どうする?最適解まとめ
ここまで、windows11 アップグレードできないpc をどうするか、様々な選択肢を見てきました。
結局のところ、「これが全員にとっての正解」というものはありません。あなたのPCの状況と、あなたが何を優先するかによって、取るべき道は変わってきます。
あなたの状況別・推奨アクション
- CPUは新しいのに非対応と言われた人
- → セクション4(BIOS/UEFI設定)を試す
TPMやセキュアブートが無効なだけかも。設定変更で公式アップグレードできる可能性大です。 - CPUが古く(第7世代以前)、メインPCとして安全に使いたい人
- → セクション7.1(ESU)または 7.2(買い替え)
非公式アップグレードのリスクは避けるべきです。まずはESU(特に無料オプション)で1年間延命し、その間に買い替えを計画するのが最も現実的です。 - PCが古く、データが消えてもいいサブPCで、技術的好奇心がある人
- → セクション5(Rufus)
セクション6のリスク(更新停止・不安定化)をすべて承知の上で、自己責任で試すなら…という選択肢です。メインPCでは絶対にダメですよ!</b/dd> - コストをかけず、セキュリティも維持したい人
- → セクション7.1(ESUの無料オプション)または 7.3(Linux)
まずはESUの無料オプションが手軽です。それが切れた後、Linuxに挑戦するのも良いかもしれません。
Windows 10のサポート終了は、PCのセキュリティについて見直す良い機会でもあると思います。ご自身の状況に合った、後悔のない選択をしてくださいね。

